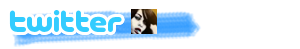FictionClose
DiaryClose
Article
ヌルくヌメった水の中
雨、というよりも滝壺に街全体が入り込んだ昼下がり、下水処理能力をはるかに超えた雨水は、入り組んだ路地のすべてをいつしか緩やかに流れる川に変えた。その表面は激しく降り注ぐ雨粒のため、蠢く瘡蓋が蝟集するようで気味が悪い。小枝や葉または何か未成熟な果実は、無数にあらわれては消える突起の先端だけを避けるように蛇行しながら流れるものの、セブンイレブンの緑色のロゴやカーネルサンダースなどが印刷されたビニール袋は、たえず殴りつけられて浮かんだり沈んだりを繰り返していた。
『……臨時政府当局は本日の記者会見において、今月初旬からの豪雨による洪水で死者が八十七人に上ったことを明らかにしました。洪水被害は東北部から中部まで三十五県に拡大し、家屋の浸水などによって約二五〇万人が影響を受けています。また保健省の情報では、衛生状態の悪化から二十五万人以上が現在皮膚病などの病気に罹り、更に伝染病の発生等が懸念される旨を発表しています。……』
彼らはガラスで出来た玄関の引き戸の前に坐っていた。この雨ではどこにも出かけられない。しかたなく雨や氾濫した流れを見、またその音を聞き、一言二言会話を交わしては眠り込むということを繰り返していた。背後から流れ続けるテレビの音声には二人とも心底倦んでいた。ここしばらくのあいだずっと同じことばかり繰り返し続けているのだ。
ナームトゥアムヤイカー。チャアンタラーイマークマーイカー。
けれども彼らもまた、雨の話や洪水の話しかすることがないのだ。
「こういう空のときってすごく雨が降るの」
彼女に促されて彼は頷く。
空はぶあつい雲に覆われていて全体に黄土色だが、よく見ると鮮やかな黄色い部分と黒を混ぜて土色じみた部分が内部でだけ動き、どこにも流れていく気配のみえないそれが向かいの家の屋根まで垂れ下がっていた。息苦しさを感じさせるほどだ。
雲を抜けてきた光も黄土色で濃淡がない。何かを反射させたり影を作ったりするのには光が弱すぎるのだ。遠くは煙るような雨に隠されて目に見える範囲全体を平板に作り変えてしまっている。まるで黄色いサングラス越しに見る、奥行きのまったく感じられない書割のようだった。
「日本ではこういう空の色も、こんな雲も一度も目にしたことがなかった」
「ここでもめずらしいと思う。だって二年とか三年に一回あるかないかじゃなかな」
男は記憶にある雲のサンプルを取り出してみたのだ。――そうだ。この色の空をはじめて見たときに、彼は確かに世界の終わりの景色を想ったのだった。
時計の針はようやく午後三時を過ぎたばかりだが、夕暮れ時のような景色がもう何時間も続いていた。時間の感覚を失い、永遠に終わることのないたそがれの世界に迷い込んだようだ。
黒々とした暗雲も激しい雷もそれだけで不吉なものだが、いま見上げるこの空はまったく得体が知れない。うすぼんやりとした均一な光が引き伸ばされ、のっぺりと視界全体を包んでおり、その空間をただただ激しい雨が落ち続けるだけだ。雷鳴すら聞こえず、繰り延べを施された時間をやんわりと圧迫するように、厚く垂れ込めた黄土色の雲はすぐそこに低く、たえず内側に内側に裏返り続けていた。
「雨、やみそうにないな」
「うん」
「フォンは雨、好きか」
男は女に問いかけてしまってから苦笑した。くだらない冗談を言ってしまったようで後悔したのだ。
〝フォン〟 チョープ 〝フォン〟 マイ
「うーん、自分の名前だからね、やっぱり好きかも。眠るのにはいい天気だし」
≪……濁流に流される人の悲鳴が、上空を旋回するテレビ局のヘリコプターの爆音に掻き消され、水上で救助する人と救助される人を永久に遠ざける。水の中で上下の感覚を失った脚が虚空に突き出され、仮想的地面を走る、次に腕が出て、想像上の電柱を抱きかかえる。ディレクターは高視聴率と一段と高い椅子への抜擢とメディア大賞の甘い香りを正確に嗅ぎ取りながら、より低く旋回するよう無線で命令を下す。悲鳴よりも大きな声だ。溺れる人は遠ざかる意識の底、混濁した意識の裡でヘリコプターに助けあげられる瞬間を夢のように幻視している。おそらく幸福な微笑を口もとに泛かべながら息絶えてゆくのだ。レスキュー隊員たちは命綱を握りしめながら、頭上のヘリコプターを睨みつける。なぜか? カメラを意識するためだ。正直なところ、こんな濁流に飛び込み、溺れている人間に近づくことなどまっぴらごめんだ。こちらが逆に殺されてしまう。レスキュー隊員たちは、見失ってしまったという口実をヘリコプターの爆音のせいにしている。その証拠にゴムボート上の隊員は一様に、脚や腕が躍り上がる方向からはわずかばかり斜に構え、躰をねじって上空のヘリコプターをのみ凝視している。そうだ! いいショットだ。できれば、もうすこしばかり悄然とした表情は出来ないものか、レスキューたちよ。俺を救助できるのはきみたちだけなんだぞ、ニュース部署のトップの椅子さえ手に入れば、娘たちを私立の高校に進めさせてやれるし、もしかすると娘たちが私立高校でつくった美しい友人たちを家に連れて来るかもしれない。俺は余暇をふんだんに取り、娘の友人であるところの少女と屈託なく、それでいて大人の余裕をみせつけながら朗らかに会話をする。彼女たちは俺の娘たちの袖をつんつんと引っ張り、耳元に口を近づけては、あら、素敵なお父様ね、などと皇族が使う言葉でもって俺の噂話を、わざわざ俺に気づかれるようにするかもしれない。瞳を輝かせ頬を赤らめるかもしれないのだ。それらはすべてレスキューたちよ、君たちの表情にかかっているのだ。右の口唇を引き攣らせてディレクターが笑う。喉が渇いた、おい! 水をもってこい! 無線に繋がれたマイクのスイッチは、もちろん OFF だ。……≫
変化の乏しい景色に気づいてはじめて、彼は日が落ちたのを知った。水も何も闇に沈んで見えなくなっている。はじめ彼はなにかおかしいと感じ、次に意識のすべてが音だけになっていることに気付いた。勢いは幾分緩んだらしく、けれどもまだ降り続くらしい雨と水の流れる音だけが聞こえている。しばらく眼を閉じて〝ぼく〟はそれを知った。少し感覚と意識がずれていた。ほんとうの闇夜だ。あの薄気味悪い雲が、まだ空一面を覆っているようで月明かりさえない。
立ち上がり手探りで電灯をつけると、二三度点滅を繰り返した明かりで目が痛む。ガラスで出来た玄関の引き戸に部屋の内部が反射して外のようすは見えない。
フォンはいつのまにか茣蓙と枕を持ち出してきて本格的に眠り込んでいる。ぼくはガラスに映り込む彼女の寝姿を眼にして思わず吹き出し、それからぼく自身もいつのまにか眠ってしまっていたのだとようやく悟った。
振り返って部屋を眺めると、この地域がたびたび洪水被害に悩まされてきたのだろうことがよくわかる。そもそも家が地面からはかなり高く建てられているし、内部にも各部屋へは五段ほどの階段がついている。引越しをしてきた当初、ぼくは装飾のためにつけられた階段なのだと勘違いしていたが、実用的な意味合いでつくられているらしい。浸水した際の被害を最小にするためだろう、コンセントの差込口はすべて胸の高さだ。
ここまで水は上がってくるのだろうか。ぼくは新しい目で家の中の一々を見廻してから、門柱の灯りだけを残してスイッチを切った。フォンが眠る隣に腰を下ろすと尻が痛む。仰向けに寝そべった。タイルの床がひんやりと冷たい。
フォンはこちらに顔を向けて小さく寝息を立てていて、なかば開かれた厚い口唇からは歯がのぞいていた。ぼくはフォンのこの口唇が好きなのだった。飽きるまで眺めてから煙草を吸いに引き戸を開く。
夕暮れ時は薄汚なく濁った水がぼくの心を喜ばせたのだが、いまは濃密な夜が水をただ真っ黒に変えてしまっていた。門柱の上についた丸い傘の電灯によって照らされた範囲のみ雨があらわれては落ち、また時折たつ水面の波頭だけが反射して光った。
ドアのスライドする音がして、「煙草?」とフォンが問いかけてくる。
「そう」
「ほんとに止まないね」
髪の毛を真ん中でわけながら彼女がいう。素直な髪だとぼくは思う。耳の下の辺りで斜めに、前下がりに切りそろえられている。
「こんな雨の夜は、日本の詩人のことをいつも思い出す」
ぼくは彼女の肩に触れ、髪を撫でる。
「中也って人なんだけどな。こんな詩。雨は今宵も昔ながらに、昔ながらの唄をうたつてる。だらだらだらだらしつこい程だ」
口ずさむとフォンは間延びした声で「綺麗な音だね」といった。「どういう意味の言葉?」
〝彼〟は丁寧に説明してやる。その言葉に眼を瞑った彼女は一々頷く。そして不明瞭な日本語で呟いた。
「わたし は あめ です」
二つある電灯のうち一つが蠢いているのに気づいたのは、またもう少し後のことだった。雨に濡れながら階段をおりて近づくと、無数の蛆が蠢いていた。
「おい、フォンすげーぞ。ちょっと来てみな」
門柱の外側に凭れ掛るように置かれたゴミ袋はなかば水中に沈み、だらしなく開いた口からは蛆どもが柱を続々と這い上がってきていた。脚すらないそれらは、とめどなく降り注ぐ雨に流れ落ちては、またぬらりとした躰を蠢めかせながら這い登ってくる。堅強な生え抜きどもだけが電灯の球面にまで辿りつき、躰の内部を透かしてのたうち廻っているのだ。
蛆が明かりを求めるとは聞いたことがない。おそらくはなかば溺れ、なかば狂気して石造りの柱を上り詰めるようすだ。彼は雨に濡れながら、それら夥しい数の生命の躍動を見つめ続けた。
フォンは庇の下で引き攣った笑いを右の口もとに泛べている。……
※
蛆虫のぜん動めいた動きを長らく見つめていたからかも知れない。気づくと彼はある女のことをしきりに思い泛かべていた。一時期――まだ日本に住んでいた頃のことだ――彼はその女に養われていた。一日あたり三千円の小遣いだった。昼過ぎに起きだすと、テーブルに千円札が三枚のっかっている。なにか――コップやら灰皿やらで押さえられて。その金を彼はポケットに捻じ込むと、駅裏の蕎麦屋で油臭い天ざるを喰って粗悪な冷酒を呑む。「混ぜもんを」と頼むと酒となにか科学的な味のするアルコールを混ぜたものを出してくれた。エタノール臭い息を吐きながら部屋に戻ると、やがて女が帰ってくる。そしておどおどと落ち着きのない上目使いで女は彼と距離をとるのだ。無性に腹が立って、なんでもいい、彼はなにか言いがかりをつける。女は黙り込んで固く閉じてしまう。彼は女をぶちのめす。顔は殴らない。痣が出来て他人に詮索されるのが怖いからではない。ただ単純に殴るのが下手で、女の歯で拳を何度も引き裂いてしまった経験があるからだ。殴りつけられているあいだも女は一度もなにも言わないし、彼と目を合わせることもなかった。ただ泣くだけだ。その涙に彼は決まって女の演技を感じ、固くちぢこまっている躰が、ぐったりするまで蹴りつけ踏みつけにする。そして、それから。
ぐったりして表情をなくした女に――目からは目脂みたいに粘液質の涙がけち臭く流れ、脱力し、けれども視線だけは絶対に合わせない女に――彼は嗚咽しながら苦しく何度も何度も謝る。
――悪かった。もう二度とこんなことせんから。本当に悪い。なんでこうなってしまうんやろう。ほんとに許してくれ。許してくれんと、俺はこのベランダから飛び降りて死ぬ。そのほうが楽や。もう終わりにしたい。おまえを殴ったり蹴ったりすんのもう厭や。俺がおまえを殴るんは、おまえのことを愛しとるからやろ。それはわかっとるんやろう? 愛してもない女、殴る意味なんてそもそもなんもないもんな? おまえがおらんとあかんねん。ごめんなあ、ごめんなあ、痛かったやろう? 痛いやろう?
彼は涙で曇った視界にすら怯えるほどに心狭くなっており、だからこそ優しく――できるかぎり慎重にと自分に言い聞かせながら――女の服を一枚一枚脱がしはじめる。女は抵抗しない。ぐったりしてしまって、投げやりで、もう抵抗できないという演技の最中だからだ。小さい下着を取り去り、オマンコの襞を舐めつづけながら、腕を伸ばして固くなった乳首を愛撫する。それから、二時間も三時間も性交するのだ。女は苦しそうに快楽をむさぼり、男の背中に爪を立てた。疲労困憊し、お互いの粘液まみれで眠る。
昼過ぎ目が覚めると、テーブルに千円札が三枚のっかっている。コーヒーカップや、醤油さしに押さえつけられて。一年以上もそうやって暮らした。
もともと女は、なにか言うたびにすぐに顔を赤らめ、下を向いて黙り込むような性質の人間だった。いま雨に打たれながら、のたうち廻る蛆どもを見て思い出したのは、女の舌だった。出会ったばかりのことだ。
――ベロだしてみ? 動かさんようにじっとさせてみ? ほら、この鏡持って。
女は小さく尖らせた舌を、閉じた口唇から突き出してみせた。
――ちゃうって、もっとこうやって。
女は恥ずかしげに、またほんの少し舌を突き出した。〝ぼく〟は女の舌を指で摘み引きずり出してやった。女の恥じらいは、ぬるりと分厚くそして熱かった。正座した尻をもじもじとさせながら、女は潤んだ目でぼくを見た。踵を使って自慰をしているのだ。ぼくは鏡をあごでしゃくる。そして女の側に廻り込み鏡を覗きながら顎鬚で女の耳と首筋を撫ぜる。
――そう、そのまんま。じっと動かさんように、ベロ、じっとさせてみ?
女は素直に鏡を覗き込むのだが、舌は一時もじっとせず、もぞもぞと動き続けたのだった。尻もまた、もぞもぞと動き続け、頬が紅潮してくるのだ。
――うごかすなって、おまえ自分の躰も満足に使えんのか?
またある時、ぼくは貧乏臭い駅前の食堂に女を連れて行った。陳列棚に小さい皿に盛り付けられた冷たい料理が並んでいるたぐいの食堂だ。
――ほら見てみ。出し巻き、ほら。あのおっさん。箸つけるやろ、眼ぇ見いや。ほら、出し巻き箸で挟むやろ。見ててや。……な? なんで口に入れる瞬間キョロって視線上げるんやろ。キモない? そーやろキモイよな。あいつもそーやで。ちゅうかみんなやけどな。見ててみーや。ほら、コロッケ千切りました。摘みました。コロッケ見てるやろ。見てます。見てます。見てます。……ヒョイ。なん? あれ? おまえもしとんねん。正直きもくてゲロ吐きそーや。頼むからやめてくれん?
女は少しずつ少しずつ、何をするにも自然でなくなっていった。日常生活のさまざまな場面で錆び付いた人形のような動きをするようになった。落ち着きをなくし、剥いた目をぎょろぎょろさせ、たえず〝彼〟を上目遣いで盗み見るようになった。男ははじめそれを楽しみ、しだいにウザくなったのだ。
河川の氾濫によって死者は膨大な数にのぼった。風邪をこじらせて五日間魘され、六日目に起き出した彼はテレビ画面に映し出された死体の群れを目にした。河口付近に流れ着いた死体は幾百体にのぼり、遺体の回収作業は遅々として進まぬ旨をアナウンサーは深刻な表情で伝えた。画面に映し出された水死体は腐敗が進み、ガスのため膨らんだ腹を上にして、浮き身で朗らかに海水浴するようすだ。夕暮れの引き潮とともに遺体が海に流れ出てしまうのを、当局は懸念しているともアナウンサーは続ける。
彼はフォンを誘いフォルクスワーゲンに乗り込んだ。海までの道はところどころ水没している区間もあったが、大方水は引いていた。不思議な気分だった。空は青かった。
河口の死体の群れははじめまったく動かなかった。テレビで見た映像との違いは、服を剥ぎ取られたり貴金属品を盗まれたりしたようで裸の死体が目立ったことと、明らかに他殺とおもわれる死体が大量に紛れ込んでいることだった。頭と両手首を切断され身元を隠蔽されたもの、銃弾らしき傷跡のあるもの、またなかには、ご丁寧にも青いビニールシートに包まれ手足を覗かせるものまであった。
あたりは見物に訪れた沢山の人間がいるにもかかわらず、おそろしく静かだった。世の中の音という音が、残らず水の流れよりもさきに沖合いへと運び去られてしまったようだ。重い海水の上をまだらに、ある場所では速く、ある場所では混ざりこみ、土に汚れた河の水が移動を始める。
やがて夕暮れの引き潮にほどけて遺体が流れ出しはじめる。絡まりあったうちの一体がまず。続いて動揺した塊が、塊のままにゆっくりと。
幾体かの死体の上には灰色に汚れた水鳥が翼を休め、首を傾げたまま動かない。そのまま申し合わせたように沖へと視線を定めゆっくり流されていく。あたりの見物人たちがやっとなにやら話を始める。また携帯電話のカメラを向ける人間もいる。ときおり何かの加減で死体がひっくり返る場合には――それは寝返りを打つように見え、とても自然に感じられた――水の跳ね返る音が低く聞こえ、どよめきにも似た、ため息にも似た空気が見物人たちを支配する。
しかし意識をこらすと、河口から海に流れ出す水の音が耳の底にはたえず鳴っている気配がある。本当には聞こえていないのにもかかわらず、そう錯覚されるのだった。
制服を着、サングラスをかけた幾人かの警察官たちが、ハンディーカムで見物人たちを撮影している。
黒ずんで凝り固まってしまっていた血液が、上辺をすべる流れにすこしずつ溶け出す。そのさまが夕陽に照らされていた。流れはどんどん速くなっているようだった。河も海もすでに元通りの景色を取り戻しはじめていた。ただ、生臭い湿ったような、また鉄サビの軋むような臭いだけが、あたりに残っていた。けれどもその残滓すらも、夜になれば風がさらっていくのだろうと思われた。
夕陽のオレンジ色の光線は、沖合いの水平線ではじけて、幾万もの細切れになっていた。海は一頭の大きな獣のように見えた。大量の遺体を咀嚼したあとで、怠惰にいぎたなくおくびをもらし、躰をふるわせているようだ。視線の先はまだまだ昼の気配をひきずっていた。にもかかわらず、背後の頭上にはもうとっくに夜が覆いかぶさっていて、星座に数えられないほどたくさんの星がまたたいていた。彼と彼女はそれらには気づかなかったけれど、やはりふるえ続けているのだった。
フォンが一歩、堤防の階段を下りて、彼を振る返る。彼はわかったと頷く。二人は一歩一歩慎重に滑りやすい階段を下りていく。河水は静かに海水と同衾を繰り返し、そのまま艶かしい姿態で沖合いへと移動しつづけていた。
背後で、二人に向かって、誰かが大声で、何かを叫んでいる。怒鳴りつける調子だ。〝ぼくら〟はそっと微笑み合い、けれどもけっして振り返らず、ゆっくりとぬるくぬめった水の中へ足を踏み出した。
<了>
LinksClose

Jyun-bun
純文学専門サイト
≫≫≫ 純文学小説投稿サイト―jyunbun

Short Story
小説、詩、エッセイ等
≫≫≫ 小説投稿サイトShortSTORY

坂口安吾
坂口安吾専門サイト
≫≫≫ 坂口安吾のすべて

PHP掲示板
PHP掲示板ダウンロードサイト
≫≫≫ PHP掲示板ダウンロード無料

はらいそ
るさんのブログ
≫≫≫ はらいそ
相互リンク
リンクしても良いぞって奇特な方、ぜひぜひメールください。
chouchoutosensha(atmark)gmail.com