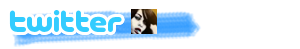FictionClose
DiaryClose
Article
川蟹の味、骨の味
帰省
ぼくの従兄に紫と書いてそのままムラサキと読ませる変わった名前の人があった。歳はぼくの一つ上だったが、幼いころぼくの両親の都合で三年ほど一緒に暮らしたこともあり、お互い遠慮をするような間柄ではなかった。
当時は顔や仕草、話し方までもがそっくりだった、とムラサキの両親――母の姉とその夫である伯父は、中学生になって体格も性格もまったく似ていないぼくらに向かってよく言ったものだ。
三年ほど暮らしたといっても、ぼくもムラサキもまだ小学校にあがる前だったので、どんなことをして遊んでいたのだかはっきりとは覚えていない。けれど幸福だったことだけは確かだ。振り返ってみればあの時期ほど屈託なく笑い、そして泣いた経験はないのではないか。
結局ぼくの両親は離婚をすることになり、ぼくは母に引き取られて大阪に住むことになった。母は朝早くから夜遅くまでぼくと彼女自身を養うため外へ働きに出ていたので、小学校に通うようになったばかりのぼくは、友達と別れてからの夕方の時間をいつも持てあました。ほとんど永遠に続くかと思われる夕暮れのオレンジ色を、躰の芯の芯にまで染み込ませて、独り狭いアパートの一室でじりじりと過ごした。
ぼくは押しつぶされそうな気分でいたのだ。まだその不安な感情が寂しさなのだとは理解できなかった。意味のわからぬ震えだす感情の裡で思い返し慰めとしたのは、やはりムラサキと一緒にいたという経験だった。それらを経験と呼んで良いのかどうだかぼくにはわからない。それというのも、思い浮かべることのできたのはほんの些細な断片だけで、どのような機会でどこで起こった出来事なのかということはまったく思い出せなかったからだ。けれども幼児のころに特有の、あの鮮やかな感情に塗れた断片たちは、ハレーションを起こした写真のように意味自体は掴めずとも、ぼくにとってはとてもあたたかかった。あたたかく感じられたそれを、ぼくは青く冷たく変わる窓外の景色から守っていたいと願ったのだった。
小学校三年生になり、ぼくは父の苗字から母の苗字に変わった。その年の夏休みから、毎年必ず母方の郷里である三重の小さな町に帰省するようになった。また従兄と再会することが出来たのだった。
ムラサキとぼくがもうすこし、たとえば二つ歳が違っていたら、従兄も兄のように振舞わなければならないと気負ったであろうし、ぼくのほうもなんとなく気後れしただろうと思う。子ども時分の年齢差は、大人になってからのそれとは比べものにならない。
けれども一年に一度、夏休みのすべてを使って母方の田舎に帰省すると、きっかり一年の歳月が過ぎたことを感じるのは出会ってほんの五分ほどのことで、すぐにも軽口を叩きあい打ち解けて、なんだかんだと遊んでいた記憶だけが残っている。
母の郷里は三重県尾鷲市近くの小さな町だった。その町のほとんどすべての家の玄関には、ぼくの新しい、まだ馴染むことのできない苗字を書いた表札が掲げられていた。海に近く、潮の匂いが強く、けれども漁業のための港で海水浴は出来なかった。そのためムラサキと連れだって遊んだのはもっぱら川だった。
深緑色した川蟹をとって食べた記憶がある。ぼくらはそれほど深くはない川に次々飛び込み、浮かび上がってしまわないように水の中で肺の息をすべて出しきってから素早く潜った。澄んだ川の流れはぬるかったが、木陰で陽の当たらない場所だけはひやりと冷たかった。それだけ流れが緩やかだったのだ。絶対に掴まえることの出来ない速く動く小魚に見守られながら、川底の石をめくる。と、蟹は暗がりで鈍くまどろんでいるのだった。
煮たり焼いたりなどしない。生きたまま食べた。威嚇したり暴れたりする蟹の両方の爪の根元を持ち、そのまま引き抜く。汁が溢れる。それを音をたてて吸う。爪の部分に少しだけある肉はあとに置いておく。川原の丸みをもった砂利の上にでも放り出しておくのだった。
もぎとられ本体を失っても爪は、太陽に焼かれた石の熱さを感じるのだろうか。痙攣するように素早く、あるいはじんわりじんわりと長いあいだ動き続けた。
裏返して雌ならば大きい、雄ならば小さい褌をめくり、柔らかい内部に指を突き込んでから甲羅を剥ぐ。透き通った鰓が張り出しているのでそれを毟り取る。丸出しになった蟹の内臓は蠢き、また心臓は小さく踊っている。ぼくらはまずその部分から食べた。開閉を繰り返す口に繋がった左右の内臓を指で掻きだし、舌にのせると苦味がまずやってくる。そしてそのあとにねっとりと濃厚な甘味がやってくるのだった。口の中で苦味と甘味が混ざりあうと、とめどなくつばきが溢れるのだ。
生きて動いているものを自分の手で殺し、その命そのものを食べることの快楽を、ぼくはムラサキに教えてもらった。脚を音をたてて噛んで、しがむ、あとは溢れる汁を舐める。動かなくなった爪の両端をつまんで裂き、付いてくる透き通った肉を啜る。あとは脚と同じだ。
「うまいやろう? 大阪にはこんなもんないやろう?」
ムラサキはいつもいつも左の眉を吊り上げ、得意げな顔つきでこう問いかけてくるのだった。ぼくのほうもいつもは蟹の汁でねとねとになった口元を腕で拭って頷くのだが、その日はこう反論してみた。
「でもあとで絶対にお腹壊すやんか」
するとムラサキはさもおかしい話を聞いたとばかり吹き出した。
「あたりまえじゃ、死ぬやつもおるらしいぞ。川蟹には寄生虫やらなんやら雑菌やらなんやら、ものすごぅ付いとぅらしい。ここの土地のもんは絶対に喰わんな、汚いゆうて喰いよらん。肺に穴あくゆうてまず喰わんのじゃ。阿呆どもじゃ。死ぬの怖い怖いゆうて震えとる阿呆ばかりじゃ。腹壊すん怖い怖いゆうとるくせに、そのくせうまいもんは人一倍喰いたい思うとる阿呆ばかりじゃ。そうや、ええこと教えたろか?」
「なにぃさ」
「あんな、わしらもう死んでるんじゃだ。生きとる思うやろ。思い込んどぉやろ。でもな、ほんとうはもう死んでもうとんじゃ。この蟹もな」そう言って従兄は蟹の緑色の両目をぼくの前に突きつけた。飛び出した両目はまだいびつに動いているのだった。そしてぼくは、ぼくが蟹を見ているというよりも、蟹のほうにぼく自身を観察されているような心持になったのだった。「このはらわた半分のうなった蟹もな、自分がもう死んどるなんて気づきもせん。こいつはいま、川ん中のさっきの石の下でなぁ、鼾かきよう思い込んどるじゃだ」
ぼくは笑ってしまった。
「なにゆうとんのさ、死んどったらこうやって話をしたり、こうやって蟹喰うたりできるものかよ」
「阿呆じゃだ。おまえは騙されとるんじゃ。そんならな、約束したるわ。わしが二十歳になった誕生日に、わしらがもう死んどるいうことを証明したる、約束じゃ」
そういってムラサキは食べ終わった殻を足元に落とし踏み躙った。ムラサキの言葉はぼくの中で引っかかった。二十歳の誕生日に何をするのかと想像すると、川原で夏の陽の光を浴びているにもかかわらず、ぼくの内部に拡がる暗闇は冷たくしんと静まり返るようだった。
毎夏の帰省は中学を卒業するまで続いた。中学校の男子生徒が母親と二人して電車に乗り、大阪からはるばる三重までの旅をするなんてことは、普通ではあまりないことだった。少なくともぼくは、帰省の時以外で母親と並んで外を歩くなんて経験は皆無だった。たとえば梅田の阪神百貨店の地下で、土産に持って行くための、みたらし団子を母親と買い求めている姿などを学校の友人に見られでもしたら、それこそ死ぬほどの恥ずかしさを感じただろうと思う。けれどもぼくは必ず帰省したのだった。それはやはり彼に会いたかったからだ。
――帰省いうのはおかしい。
従兄にこうたしなめられたことがあった。確かぼくが中学の二年生の夏だ。ぼくらはすでに死んでいるのだとムラサキが言った夏からしばらくたっていた。どうして? と尋ねるぼくにムラサキはこう胸を張って返答した。
――省という字にはなあ、かえりみる、はぶくという以外にも「安否をたずねる」ちう意味があって、帰省とは噛み砕いたら、故郷に帰って親の安否を気遣うということじゃ。おまえは親と一緒に住んどろうが。おまえの母親にとっては帰省でもおまえはただ遊びに来とるだけじゃだ。
ぼくはその説明を受けて納得しつつも、こう反論してムラサキを笑わせた。実際の話、ぼくはムラサキの安否をたずねるつもりでもあったのだ。
――ムラサキが死んどらんかって確かめに来よるんよ。
彼の二十歳の誕生日、何が起こるのかということをぼくは幾度も想像した。そして、ムラサキが死んでいないかどうか確かめに来るのだというぼくの言葉こそが、ぼく自身何を期待しているのかということを明瞭に主張していた。しかしぼくは実際にそれを怖れていたのだ。ムラサキがぼくの言葉を聞いて、ないしは反芻してどういった心持ちを抱くのか、また従兄が自分の言った言葉を思い出し二十歳の誕生日をどういった心持ちで待ったのか、そういったことにすら配慮が及ばないほどに僕は心底怖れていたのだ。
ぼくの予想した通りムラサキは、二十歳の誕生日に巧妙な形で自殺した。
帰郷
池袋の東口を出てキンカ堂へと歩く。近くに高速バス乗り場があるからだ。キンカ堂自体は去年閉店してしまっていた。当時閉じられたシャッターにたくさんの貼り紙がされていたのを覚えている。けれどもいまは全て剥がされ撤去されているらしい。ぼくの覚えている貼り紙の多くには『ありがとう』という文字が書かれていた。沢山のありがとうで埋めつくされていた。
信号待ちのあいだに考えていたのはそのようなことだった。どうしていま、そんなことを思い出すのかさっぱり分からなかったけれど、目の前に映像としてよみがえってくるのは、――『今までどうもありがとう』の夥しい文字だった。
クラクションを鳴らされながら信号を渡り、左手にビックカメラを過ぎて、中央分離帯にある時計を見上げる。時刻は午後九時少し前だった。まだまだ時間がある。出発は九時四十分だったはずだ。念のためにと時刻だけを走り書きしてきた煙草のボックスをポケットから取り出し確認する。その途端、ぼくは朝からまったく煙草を吸っていなかったことに気がついた。あちこち手を突き込みライターを探すが見つからない。しかたなくマクドナルドに入って時間を潰すことにした。気づけばぼくは煙草だけでなく、朝からなにも口にしていなかったのだ。食欲はまったくといっていいほどなかった。けれども何かしたいと思ったのだ。何でもよかった。人間らしいこと、生きているものがするようなことを何かしらやっていたかった。
午前中、大阪の母親から携帯に電話を貰ったのだった。ぼくは大学の授業をサボり、アルバイトをしている最中だった。そのため着信には気づかず、連絡がついたのは昼の休憩時間だった。ムラサキが死んだときいて、ぼくは慌て、そして予想通りだったことにも思い当たった。
どうしてぼくはムラサキに電話をかけて、彼がしようとしていたことを止めなかったのか。ムラサキの自殺をぼくはずっと以前から確実に予想していた。けれども電話をかけて、おまえは自殺をしようと考えているのだろうなどと言うことは出来なかった。もしムラサキが自殺をすることなどまったく考えていなかったとしたら、逆にぼく自身がもっとも怖れている答えを彼に与えてしまうことになるかもしれない。無意味な死へと彼を突き飛ばしてしまうかもしれない。またぼくらがまだ中学生だったころのことだ、ぼく自身は従兄を思い出すたびごとにあの約束を思い出したが、ムラサキ本人はあの川原で話したことをすっかり忘れてしまっているかもしれなかった。
ぼくは幾度も幾度もためらったが、電話をかけることはなかった。いつも頻繁に連絡を取り合っていたにもかかわらず、ここひと月のあいだは恐ろしくてメールさえ避けていたのだ。
母との電話を切ってすぐに店長にわけを話し、アルバイトを早退させてもらった。ぼくはとにかく一度自分の部屋に戻ることにしたのだ。震えが止らない指でキーボードを叩き、ネットで三重までの高速バスを調べた。予約の電話をかけ、二泊分の荷造りをした。そこまでは記憶にあった。
部屋を出たのは午後八時半だった。昼過ぎからの六時間近くを、ぼくはどうやって過ごしたのだろう。
泣かなかった。それだけは確かだった。どうしても泣けなかったのだ。そうだ、ぼくはトイレの便座に座っていたのだった。でも、なぜトイレだったんだろう。便座に腰をかけて、なぜ泣けないのだろうと不思議に思っていたのだ。そして思い出したのは、これと似た気分を最近味わったということだった。
大学の友人が死んだのはいつだったか、二ヶ月前だろうか、それとも半年前だろうか、もしかすると一年前だったかもしれない、判然としなかった。とにかく異様に肥満した男だった。白血病だったときかされた。ぼくらは友人が死んでからはじめてそのことを知ったのだった。いつも黒い服に黒いズボン姿でどことなく飄々としており、「黒は痩せて見えるから」などと笑っていた。ぼくらはカフカとあだ名していたが、肌の色は女みたいに白かった。
テレビからの影響だろうか。肥満した男が白血病を持っているなどと思いもしなかった。ぼくがイメージしていた白血病患者は、美しく線は細く、影が薄く、そしてなぜか若い女性であった。
カフカが死んだと電話で聞いたときも、ぼくは便座に座り、なぜ泣けないのだろう、ぼくは冷たい人間なんだろうかと自問したのだった。けれどもどうしてトイレの中に篭らなくてはいけなかったんだろう。
あるいは、トイレは天国に繋がり、台所は地獄に繋がっているからかもしれない。そう言っていたのはだれだったか。ムラサキだっただろうか。八重機千々端姫という美しい女神がトイレにはいるのだそうだ。またトイレは生と死の狭間の場所でもある。時折『自分』をトイレの中に置き忘れる人もあるらしい。人間がもっとも動物に帰る場所であることを考えると、それももっともなことだと思われてくる。排泄という死を生から剥がし落とす時に、文字通り『自分』自身をも排泄する人間がいるということは、俄かにもっともなことだと思われてくる。
母がまだ幼いころ、こんなことが便所であったんだと話して聞かせてくれたことがあった。母方の曽祖父はちょうど百年前の、あの大逆事件に関わりのあったらしい人物であった。田舎の狭い町のことである。当時は小字よりもまだ小さな集落に過ぎない土地だったらしいのだが、人々から散々アカだのなんだのと罵られいじめ抜かれたらしい。村八分は公然と行われていたのだった。
死の間際、床に伏せっていた曽祖父はある日の昼下がり突然姿をくらました。ほんの十分ほど目を離した隙にである。歩くことなど絶対に不可能だったはずであるのにと、家族のものは訝りながらも、家の中を手分けして探した。が、どこを探しても見つからない。警察に相談しようと意見が一致しかけたところで、ようやっと母がそれに気づいたのだそうだ。
「離れにな、離れて言うてもほら、おまえも知っとるやろ、あの鯉泳がしとる池の裏側。あそこにもう使わん鎌やらなんやら突き込んどる小屋があったろ。あそこに便所があったんや。そう、いまは母屋の前まで移動させとる便所。うちはまさかこんな所にいるわけない思たけども、念のため見てきてて、お母さんが言わはったん。ああ? そうそう、うちの本当のお母さん。おまえの知っとんのは、あれは違う。あれは嘘のん。あとから来たどっかの後家さんや。うちの本当のお母さんも早うに亡うなってしもたけどな、そのころはまだ元気やったんよ。それでなあ、小屋の便所にいったら、南京錠がかかっとんの。外からよ。そんなもん前の日まであらへんからねえ。おかしい。うちはお母さん所に戻って袖引っ張って言うたん。『お母さん、便所に鍵かかってんでえ』て。『何言いよるんよこの子は』とお母さんは応えた。それでもお母さんに手ぇ繋いでもろてもう一度いったら、やっぱり。『あらなんでぇ』とお母さんも驚いた。とりあえずお父さんがくぎ抜きで、壊したんよ、南京錠で止められてる金具の根元。木ぃなんて腐ってもてて、ぐちゃぐちゃやから、すぐや。開けたら、そう、その通り。お祖父さんうす暗い便所の隅に座てね。尻紙置いてあったとこに座り込んでなんやらぶつぶつぶつぶつ言うとるの。目ぇギラギラさせて小そうちぢこまってはった。気色悪りぃてねえ。あの時ばかりは驚いた。顔なんか朝までのお祖父さんとぜんぜん違うの。どうやってこんな所に来たんですかてみんなで訊いたけども、お祖父さんぶつぶつぶつぶつ独り言するばっかりや。けども一番おとろしかったんは、誰が外から鍵かけたんやろういうこと。ほんの十分やそこら目ぇ離した隙におらんようになって、家のもん皆で探してたわけや。誰も他のもんなんかいやせんし、もともとそんな時間なんてあらせん。音もせなんだからねえ。家のもんは便所の神さんに呼ばれたんやろうと言いあっとったけどの。お祖父さんがぶつぶつずぅぅと言いよるの、てんのうへいかさまてんのうへいかさまてんのうへいかさま。便所の神さんはおとろしけどな。もともとは宇佐の神さん、海の底の神さんやから、天皇陛下とは仲悪りぃ思うけどなあ。やっぱりあれやで。アカや逆賊やいうていじめ抜かれたけどな。大逆の時は処刑されとる人らもおったわけや。最後に気持ちよう布団の上で死なれたら堪らん、腹の虫が納まらんいう人らがぎょうさんおったんかもしれんなあ。おまえもよう覚えときや。一番おとろしのは鬼やないで、神さんやないで、一番おとろしのは人間や。にこにこしてしれぇとしてこんにちはぁ言うとる人間や」
曽祖父は天皇陛下の名前を低く唱えつづけ、疲れ果てた一週間後、ほっとしたように亡くなったそうだ。
母はまた、従兄の名前がムラサキであることも曽祖父に関係があると言った。社会主義者であった曽祖父がアカだと罵られいじめ抜かれていたことで、はっきりさせない――混ざり合った色の名前を伯母がつけたがったとのことである。どのような高い志を持っていようとも、強い主義主張はときに人を殺すものなのだから、自分の息子だけにはそうなって欲しくなかったのだろう。
バスの中でぼくは少し眠った。東京をバスで発った夢を見、座席の振動と機関音で目覚める。夢の中には現実の振動も排気音も紛れ込んでいたのだし、目覚めても夢の延長がそのまま現実へと繋がっていた。夢と現実の狭間はバスの移動とともに少しずつその距離を縮め、ぼくはまどろみの中で川蟹を見た。川底の石の下にもぐりこみ、鈍く眠っていた当時の蟹どもではなく、いままさに熊野のあの川で活発に捕食を繰り返しているであろう野蛮な川蟹を見た。タイヤが一定のリズムでたてる、高速道路特有の擦過音がまた眠気を誘う。
早朝にバスは尾鷲に着き、バス降り場まで伯母が迎えに来てくれていた。
「悪りぃことしたねえ、学校は大丈夫な?」
伯母は目を腫らしていた。緑色のトラックで迎えに来てくれていたのだが、どうして伯母は自分の軽自動車で来なかったのだろう。ひと月ほど前に新車で買ったばかりだと母から聞いていた。不審に思いぼくは口を開きかけた。けれどもふと気づき、なんとか黙っていることができた。
トラックは国道に出て海へと向かう。ちょうど昇りつつある朝日を目指して走るのだった。熊野灘は凪いで、朝日を浴びて鏡面のように輝き、穏やかに眠たげだった。
海岸線に沿った道に出てからやっと伯母は口を開いた。泣く伯母の姿は見たくなかったので、ぼくは助手席側に広がる低い堤防越しの海を眺めながら話を聞いた。
従兄は二十歳の誕生日の前日である一昨日、近所の酒屋に自分で出向きビールを四ケース買った。
伯母がどうしてこんなに沢山買い込んだのだと訊いてもただ笑っていたのだそうだ。とくにいつもと変わったようすはなかったと伯母は言った。けれどもきのうの朝、伯母がムラサキを起こすために部屋に入っていくと、すでに彼は死んでいた。
「おかしな子ぉや。ほんまに」
ムラサキは首を括って死んだとはいえる。けれども首を吊ったとはいえないのだった。彼はビールケースを二段重ねて部屋の隅に置くと、同じように重ねたものを逆側の隅に置いた。ロープを一段目と二段目に頑丈に縛りつけて部屋の隅と隅で渡し、部屋の中央に正座していたらしい。もし悪臭がしなかったならば、伯母はムラサキがもう起きているのだと引き返すところだった。ムラサキは顎の下辺りでロープを二巻きにし、少し前のめりになって膝に硬く握った両手を置いて死んでいたそうだ。
「何考えとるんやろうねえ。ほんまに阿呆や。戻ろう思たらいつでも引き返せる思たんやろうか。なんや知らん腹立ってきてねえ。首吊るんやったら、台の上へのって足場を蹴飛ばしてしもたら後戻りできへん。どないに足掻いたところでもうあかん。けども正座しとる、死ぬのやめよ思たら、ちょい、や。首をちょっと、五センチも持ち上げたらしまいや。なんや悔しいてね。あと遺書ら、なんと書いとったと思う? ごめんなさいも、いままでありがとうもなし……ふつ……う」
伯母はそこで声を震わせた。
「普通な、遺書っていうたら先立つ不幸をお許しくださいやろう? あの子こう書いとったん。『わしの通夜と葬式、ビール四ケースで足りるか?』それ読んだらもうなんや知らん、ほんまに腹立ってきてねえ」
トラックは家までの細い上り坂を喘ぎながら上りきり、綺麗な紫色の軽自動車の隣に停められた。
ぼくはしたたかに酔った。葬式のあいだじゅうぼくは呑み続けた。坊さんがお経を上げているあいだも独り別の部屋に篭って呑み続けた。親族らはぼくをいさめにくる母に向かって、あの子が一番つらいんだからと泣き笑いのような顔で言っていた。しかしぼくはただ甘えていたのだ。読経の声は低く高くいつまでも続き、家の中にいるのは辛気臭かった。
「こないな綺麗な形で残ることはめったにありません、仏さんが座禅を組んでいる姿ですなあ。生前に良い行いをしていた証拠です」
焼き場の職員は箸で白い第二頸椎を胸の高さに掲げ、その下に左手を添えながら言った。
「はじめに歯を拾うてください。それから足、腕、腰、背、肋骨、頭部の順で骨壷に入れてください。最後に故人と最も縁の深いお二人様で、喉仏を拾うてください」
職員は滑らかな口調で続けた。
ぼくは一度もムラサキの死に顔は見なかったが、それもただ気が進まないからなんだと思った。なぜだかすでにこころの整理がついているような心持だった。先ほどまで飯を喰い酒を呑んで噂話に笑い声を上げていた親族らが、焼けた骨を前に再度涙を流し、センチメンタルな悲しみに浸っているのが堪らなく穢らしく見えた。泣きながらも次々と、まるで片付けものでもするように骨を納めていくのだ。
「何しよるんよ!」母親がぼくに向かって叫んだ。「あんた何しよるん、喰うとぉるんちゃうやろね、うわ、何しよんよ。姉さん、この子ムラサキの骨喰いよるわ、ちょっとあんたやめえ、出しぃ、ほら、阿呆、ここに出しぃって、姉さん!」
ぼくは仏の形をした粉っぽい骨を音をさせて噛み砕き、笑った。熱い。ほふほふ息を吹きながら舌で転がし、また歯で崩す。ムラサキの残骸は、苦味もまたもちろん甘みもなく、まったくの無味だ。
ムラサキの母親が飛び掛るようにやってきて、ぼくの口を開かせようと右手であごを掴んできた。
「おまえ何しよるかわかっとんのか!」
伯母は目を剥いて叫んだ。おそろしい力だった。
舌にこびり付く砕片だけを残してぼくは大きな塊を飲み下し、ムラサキの母親の手を振り払い睨み返した。
「わしがいまからムラサキじゃ。おのれらよう聞きさらせ、わしがムラサキじゃ!」
おそろしい形相をしている親族一同に向かってぼくはそう叫び、それから粉っぽい唾を吐いてあかんべえをしてやった。
すると突然、ぼくはどうしてだか笑いだしてしまった。焼き場の職員たちがこそこそ耳打ちしているのを見たり、白内障を患った伯父が、何が起こったのかとすぐ近くにまで寄ってきて鼻面をあげて目を細めたり、子どもらが一斉に引き裂くような泣き声をあげたり、さっきまでめそめそ泣いていた祖母が骨壷に向き直って数珠をならし、低い声で聞きかじりのお経を唱えだしたり、そういったことすべてが堪らなく可笑しかった。笑いはぼく自身ではもう止めようがなくなるほどにまで膨れ上がっていた。塩っからい涙を流しながら、痛む腹を抱え、ぶつぶつコーラのあぶくのように溢れ出し続ける笑いを、ぼくはいつまでもいつまでも甘く吸わぶるように笑った。
耳の奥にはムラサキの川原で言った言葉がよみがえってきていたのだ。
――死ぬの怖い怖いゆうて震えとる阿呆ばかりじゃ。腹壊すん怖い怖いゆうとるくせに、そのくせうまいもんは人一倍喰いたい思うとる阿呆ばかりじゃ。
<了>
LinksClose

Jyun-bun
純文学専門サイト
≫≫≫ 純文学小説投稿サイト―jyunbun

Short Story
小説、詩、エッセイ等
≫≫≫ - 小説投稿サイト-ShortSTORY

坂口安吾
坂口安吾専門サイト
≫≫≫ 坂口安吾のすべて

PHP掲示板
PHP掲示板ダウンロードサイト
≫≫≫ PHP掲示板ダウンロード無料

はらいそ
るさんのブログ
≫≫≫ はらいそ
相互リンク
リンクしても良いぞって奇特な方、ぜひぜひメールください。
chouchoutosensha(atmark)gmail.com