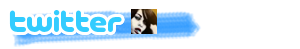FictionClose
DiaryClose
Article
そこにいない人を思い出す契機――村上春樹『午後の最後の芝生』について
何かを放り込む
村上春樹の初期の作品に『午後の最後の芝生』という短編小説があるのですが、とても評価の高いものだそうです。ぼくもとても好きな作品の一つなのですが、通常、デタッチメントやコミットメントという文脈で語られることの多い作品です。
今回は、その作品にあらわれる傍点つきの
物語の後半の部分――芝刈りに行った先でそこに住んでいる大柄の女性にサンドイッチをご馳走になり、その女性の娘(おそらくは死んでしまった)の服を見せられる場面です――をすこし引用してみます。
まず、「どう思う?」と訊ねるこの時点では「彼女」とは大柄の女性をさします。そして、大柄の女性は、すっと「彼女」という代名詞の場所を空けて、そこに自分の娘を代入します。傍点つきの「「どう思う?」と彼女は窓に目をやったままいった。「
彼女 についてさ」
「会ったこともないのにわかりませんよ」と僕は言った。
「服を見れば大抵の女のことはわかるよ」と女は言った。
娘の服に誘われるように「僕」は別れをきりだされたばかりの恋人のことを思い出します。どんな服を着ていたか? しかし漠然としたものしか浮かび上がってきません。スカートを思い出そうとするとブラウスが消え失せるといった具合です。
娘の服はこの場合、比喩的にいえば代名詞としての役割を持っているように感じられます。目の前にある服は女性用のものであることから、「女の娘」と「僕の恋人」が繋がる。着られていない服(空白)という回路で否応なく繋がってしまう。そして、恋人の服装を思い出そうとするわけです。しかし思い出せない。なぜなら僕は本質的には恋人とデタッチメントの関係にあったから。そして、こう続けられます。
ここで、「彼女」という代名詞は三回登場します。前二回の傍点つきの
彼女 の存在が少しずつ部屋の中に忍びこんでいるような気がした。彼女 はぼんやりとした白い影のようだった。顔も手も足も、何もない。光の海が作りだしたほんのちょっとした歪みの中に彼女はいた。僕はウォッカ・トニックをもう一杯飲んだ。
もしかしたら、とぼくはおもいます。もしかしたら、この部分では「彼女」に「僕」すら代入されているのではないか? すべての事柄と本質的にデタッチメントの関係にある、恋人、ぼく、大柄な女性の娘。その時代(あるいは今現在もそうかもしれません)の若者が共通するものとして持つ性向してのデタッチメント。「ボーイ・フレンドはいます」と僕は続けた。「一人か二人。わからないな。どれほどの仲かはわからない。でもそんなことはべつにどうだっていいんです。問題は……彼女がいろんなものになじめないことです。自分の体やら、自分の考えていることやら……そんなことにです」
「そうだね」としばらくあとで女は言った。「あんたの言うことはわかるよ」
ヘミングウェイの短編小説に『何を見ても、何かを思い出す』という題名のものがあります。ぼくも絶えず、
人はそうやって何かを引きずりながら生きていくものかもしれません。否応なく引き込まれるデタッチメントからコミットメントという通路を通って――。
< 了 >
参考
『村上春樹の短編を英語で読む』 加藤典洋著
『村上春樹イエローページ』 加藤典洋著
LinksClose

Jyun-bun
純文学専門サイト
≫≫≫ 純文学小説投稿サイト―jyunbun

Short Story
小説、詩、エッセイ等
≫≫≫ 小説投稿サイトShortSTORY

坂口安吾
坂口安吾専門サイト
≫≫≫ 坂口安吾のすべて

PHP掲示板
PHP掲示板ダウンロードサイト
≫≫≫ PHP掲示板ダウンロード無料

はらいそ
るさんのブログ
≫≫≫ はらいそ
相互リンク
リンクしても良いぞって奇特な方、ぜひぜひメールください。
chouchoutosensha(atmark)gmail.com